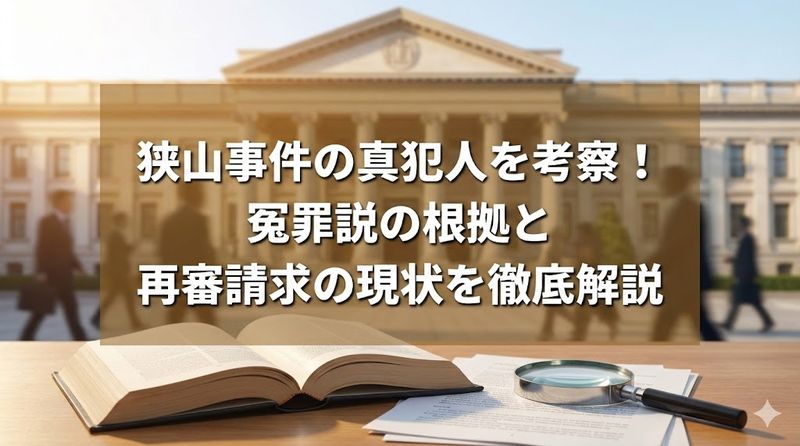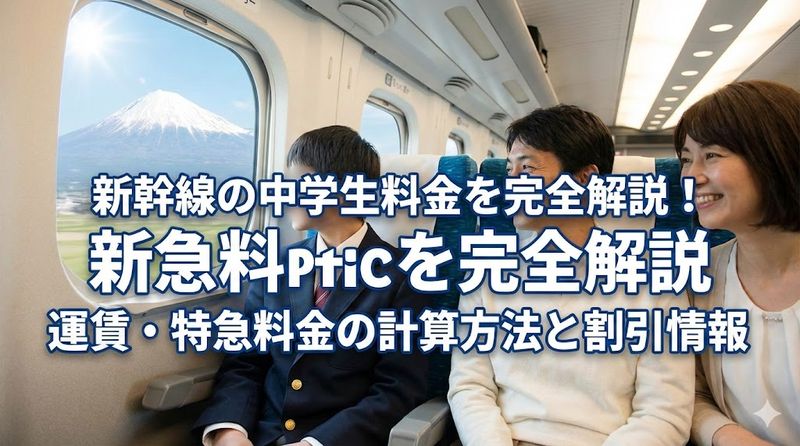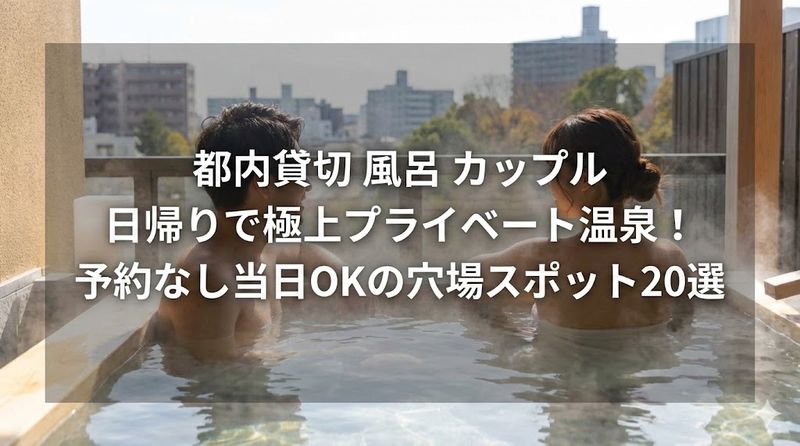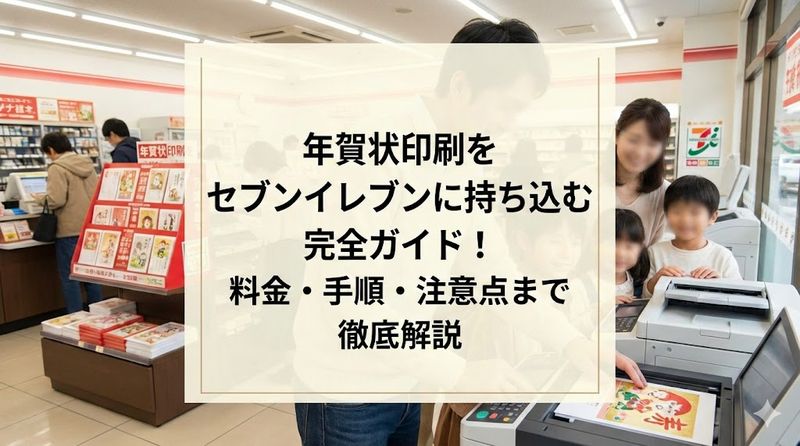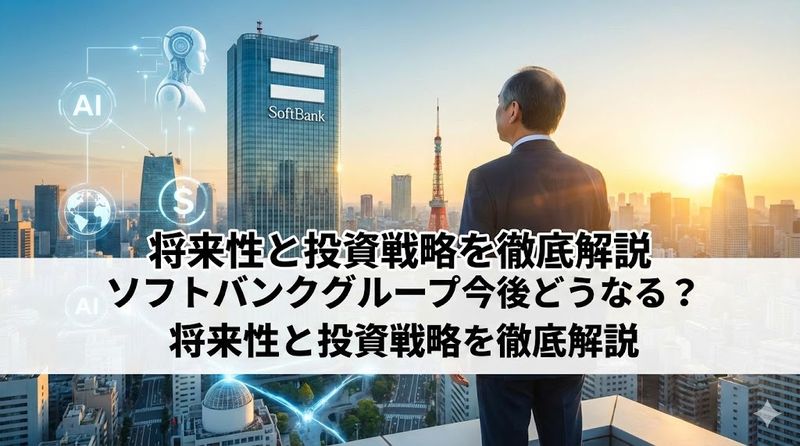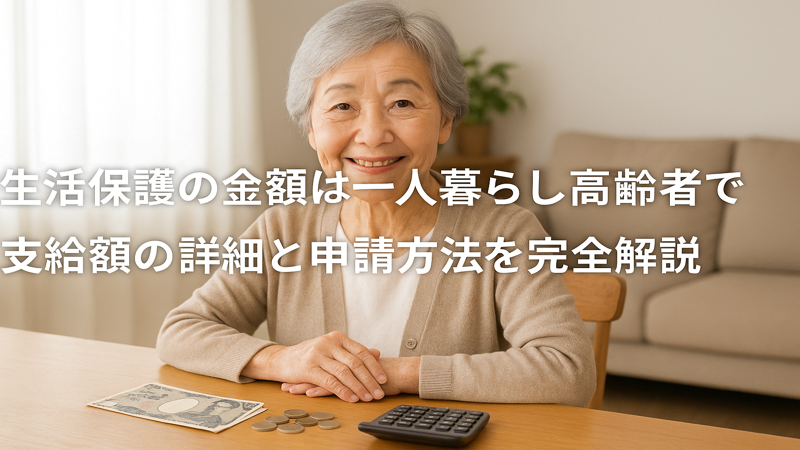
あなたは一人暮らしをしている高齢者で「年金だけでは生活が厳しい」「生活保護はいくらもらえるのだろう」と悩んでいませんか?結論、一人暮らしの高齢者でも条件を満たせば生活保護を受給でき、東京23区では月額約13万円程度の支給を受けることができます。この記事を読むことで、高齢者の生活保護支給額の詳細や申請方法、受給条件がわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。
Contents
1.生活保護の金額は一人暮らし高齢者でいくらもらえる?

東京23区在住65歳以上の支給額シミュレーション
東京23区(1級地-1)に住む65歳以上70歳未満の一人暮らし高齢者の場合、生活保護費は月額約13万580円となります。
内訳は以下の通りです。
- 生活扶助基準額:76,880円
- 住宅扶助:53,700円
生活扶助は食費、被服費、光熱費などの日常生活に必要な費用を賄うものです。
住宅扶助は家賃として支給され、東京23区では53,700円が上限となっています。
ただし、この金額は収入がない場合の満額支給です。
年金などの収入がある場合は、最低生活費から収入を差し引いた額が支給されます。
地方都市での高齢者一人暮らし支給額比較
地域によって生活保護費は異なります。
地方都市では東京23区より1~2割程度低くなるのが一般的です。
例えば、2級地や3級地では以下のような金額になります。
- 2級地-1の場合:約11万~12万円
- 3級地-1の場合:約10万~11万円
また、寒冷地では冬季加算として暖房費が上乗せされることもあります。
北海道や東北地方では、10月から4月まで月額1万2,780円程度の冬季加算が支給される場合があります。
住宅扶助の上限額も地域によって大きく異なり、地方では3万~4万円程度となることが多いです。
年金受給者の生活保護費差額計算方法
年金を受給していても、金額が最低生活費を下回る場合は生活保護を受給できます。
計算方法は非常にシンプルです。
生活保護支給額 = 最低生活費 - 年金収入
例えば、東京23区在住の65歳で月額4万円の国民年金を受給している場合:
- 最低生活費:130,580円
- 年金収入:40,000円
- 生活保護支給額:90,580円
このように、年金だけでは足りない分を生活保護で補うことができます。
年金と生活保護は併用可能であり、決して恥ずべきことではありません。
月収4万円の年金受給者の実際の支給例
国民年金のみを受給している高齢者の実例を見てみましょう。
東京都在住の68歳女性の場合:
- 国民年金:40,000円
- 生活扶助:36,880円(76,880円-40,000円)
- 住宅扶助:53,700円
- 合計受給額:90,580円
大阪府在住の66歳男性の場合:
- 国民年金:42,000円
- 生活扶助:約25,000円
- 住宅扶助:約40,000円
- 合計受給額:约65,000円
このように、年金収入があっても生活保護との併用により、最低限度の生活が保障されます。
2.一人暮らし高齢者が生活保護を申請する条件

収入が最低生活費を下回る基準とは
生活保護を受給する最も基本的な条件は、世帯の収入が厚生労働大臣の定める最低生活費を下回ることです。
最低生活費は以下の要素で構成されます。
- 生活扶助(食費、光熱費など)
- 住宅扶助(家賃)
- 各種加算(冬季加算、母子加算など)
高齢者一人暮らしの場合、教育扶助は対象外となりますが、医療扶助や介護扶助は重要な要素となります。
収入には年金だけでなく、就労収入、親族からの援助、保険金、相続なども含まれます。
つまり、これらすべての収入を合計しても最低生活費に満たない場合に、生活保護の対象となるのです。
高齢者の資産活用と処分が必要なもの
生活保護は最後のセーフティネットであり、まず利用可能な資産をすべて活用することが前提です。
処分が必要な資産には以下があります。
- 預貯金(生活費として使い切る)
- 土地・建物(売却価値がある場合)
- 自動車(通院等で必要な場合を除く)
- 貴金属、宝石類
- 生命保険(解約返戻金がある場合)
ただし、やむを得ない事情がある場合は保有が認められることもあります。
例えば、持ち家でも売却価値がない場合や、売却すると生活に支障をきたす場合は保有が認められることがあります。
賃貸住宅や社用車などは個人の所有物ではないため、手放す必要はありません。
扶養義務者からの援助優先の原則
生活保護法では、扶養義務者からの援助が生活保護に優先すると定められています。
扶養義務者とは、本人から見て三親等内の親族を指します。
高齢者の場合、具体的には以下の人たちです。
- 子どもや孫
- 兄弟姉妹
- 甥・姪
ただし、扶養義務者に援助能力がない場合や、援助を受けることが困難な事情がある場合は生活保護を申請できます。
また、DV被害や家族関係の断絶がある場合も扶養照会を避けることが可能です。
自己申告制度が採用されており、受給者が必要以上の援助を求めない限り、具体的な援助状況を報告する必要はありません。
他の制度利用後の最終手段としての位置づけ
生活保護は「最後のセーフティネット」として位置づけられています。
申請前に以下の制度の利用を検討する必要があります。
- 生活福祉資金貸付制度
- 各種年金制度(障害年金、遺族年金など)
- 住居確保給付金
- 自立支援医療制度
高齢者の場合、特に介護保険制度や後期高齢者医療制度の活用が重要です。
これらの制度を利用してもなお生活が困窮する場合に、初めて生活保護の対象となります。
公的融資制度で現状を打開できる場合は、まずそちらの利用が優先されます。
3.生活保護の8つの扶助と高齢者が受けられる支援内容

生活扶助で支給される食費・光熱費の内訳
生活扶助は日常生活に必要な基本的な費用を賄う最も重要な扶助です。
具体的には以下の費用が含まれます。
- 食費(栄養バランスを考慮した最低限の食事)
- 被服費(季節に応じた衣類)
- 光熱水費(電気・ガス・水道代)
- 移送費(通院等に必要な交通費)
- 日用品費(生活用品、消耗品)
東京23区在住の65歳以上高齢者の場合、月額76,880円が基準額となります。
この金額は第1類(個人の基本的需要)と第2類(世帯共通費用)で構成されており、一人暮らし世帯には第2類として一律27,790円が加算されます。
居宅で月単位で金銭支給されるため、計画的な生活設計が可能です。
住宅扶助の上限額と賃貸物件選びの注意点
住宅扶助は家賃として支給される重要な扶助です。
地域別の上限額は以下の通りです。
| 地域区分 | 単身世帯上限額 |
|---|---|
| 東京23区 | 53,700円 |
| 大阪市 | 40,000円 |
| 名古屋市 | 37,000円 |
| 福岡市 | 32,000円 |
住宅扶助の範囲内でしか賃貸物件に入居できないのが原則です。
上限を超える物件に住み続ける場合は、超過分を生活扶助から支払うか、ケースワーカーから転居指導を受ける可能性があります。
ただし、転居が必要な場合の引越し費用や火災保険代は生活保護から支給されるため安心です。
高齢者の場合、孤独死リスクを理由に入居審査で断られることが多いため、生活保護受給者向けの物件を探すことが重要です。
医療扶助による医療費無料化のメリット
医療扶助は高齢者にとって極めて重要な扶助です。
生活保護受給者は医療費が完全に無料になります。
具体的なメリットは以下の通りです。
- 診察料、検査費、薬代がすべて無料
- 入院費用も全額支給
- 歯科治療も対象
- 通院交通費も支給対象
生活保護受給者は国民健康保険を脱退し、医療扶助による現物給付を受けます。
医療機関では「医療券」を提示することで、窓口負担なしで治療を受けることができます。
持病がある高齢者や定期的な通院が必要な方にとって、大きな経済的負担軽減となります。
介護扶助で受けられる介護サービス
65歳以上の高齢者には介護扶助が非常に重要です。
介護保険制度と連携し、介護サービスの自己負担分が免除されます。
利用できるサービスは以下の通りです。
- 訪問介護(ホームヘルパー)
- 通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 福祉用具貸与
- 住宅改修費
介護認定を受けた高齢者は、ケアプランに基づいて必要な介護サービスを無料で利用できます。
生活保護受給者への金銭支給はなく、介護事業者に直接費用が支払われる仕組みです。
要介護度が高い高齢者ほど、介護扶助の経済的メリットは大きくなります。
葬祭扶助など高齢者特有の扶助制度
高齢者の生活保護では葬祭扶助の利用頻度が高いのが特徴です。
葬祭扶助は以下の場合に支給されます。
- 受給者本人が亡くなった場合
- 受給者が葬儀を行う場合
支給内容は以下の通りです。
- 遺体の運搬費用
- 火葬費用
- 埋葬費用
- 最低限の葬儀費用
ただし、残された金品からの支払いが優先され、不足分のみが葬祭扶助として支給されます。
単身高齢者の場合、親族がいないケースも多く、行政による葬儀が行われることもあります。
その他、出産扶助や生業扶助もありますが、高齢者一人暮らしの場合はあまり関係ありません。
4.一人暮らし高齢者の生活保護申請から受給までの完全ガイド

福祉事務所での事前相談の進め方
生活保護の申請前には、まず福祉事務所での事前相談が重要です。
相談窓口は以下の通りです。
- 市部:市(区)の福祉事務所
- 町村部:都道府県の保健所(健康福祉センター)
事前相談では以下の内容を確認します。
- 現在の収入状況(年金、就労収入など)
- 資産の有無(預貯金、不動産、保険など)
- 親族の援助可能性
- 他の制度の利用状況
相談時には収入や資産に関する書類を持参すると話がスムーズに進みます。
担当者から生活保護制度の説明を受け、生活福祉資金や他の社会保障制度の活用についても検討されます。
相談は何度でも可能であり、申請を強要されることはありません。
申請に必要な書類と準備すべきもの
正式な申請には申請書の提出が必要です。
申請書には以下の内容を記載します。
- 氏名、住所、居所
- 保護を受けようとする理由
- 資産及び収入の状況
- 扶養義務者の状況
申請と同時に提出が必要な書類は以下の通りです。
- 通帳の写し(過去3ヶ月分)
- 年金証書
- 給与明細(働いている場合)
- 賃貸借契約書
- 健康保険証
- 印鑑
書類が揃わない特別な事情がある場合でも申請は可能です。
民生委員に相談してから申請することも可能で、申請権を妨げられることはありません。
ケースワーカーによる調査内容と期間
申請後、ケースワーカーによる詳細な調査が開始されます。
調査内容は以下の通りです。
- 家庭訪問による生活状況の確認
- 資産調査(銀行照会、保険照会など)
- 扶養義務者への照会
- 就労能力の判定
- 他法他施策の活用状況確認
調査期間は原則14日以内ですが、特別な事情がある場合は最大30日まで延長されることがあります。
家庭訪問では居住実態や生活状況を確認し、申請内容に虚偽がないかをチェックします。
正直に状況を説明することが重要で、隠し事があると後で問題となる可能性があります。
調査結果に基づいて、保護の可否が決定されます。
受給決定後の生活で注意すべきポイント
受給が決定されると、毎月決まった日に保護費が支給されます。
受給中に注意すべき点は以下の通りです。
- 収入の変化は必ず報告する
- ケースワーカーの訪問調査に協力する
- 就労指導がある場合は従う
- 医療機関受診時は医療券を持参する
収入申告は毎月義務であり、年金額の変更や臨時収入があった場合は速やかに報告が必要です。
虚偽申告や収入隠しは不正受給にあたり、刑事罰の対象となることもあります。
ケースワーカーは年数回の訪問調査を行い、生活状況の変化を確認します。
自立に向けた支援も受けられるため、積極的に相談することが大切です。
生活保護は自立への足がかりであり、状況が改善すれば受給を終了することも可能です。
まとめ
この記事で解説した生活保護の一人暮らし高齢者向けの重要なポイントをまとめます。
• 東京23区在住の65歳以上一人暮らしでは月額約13万円の生活保護費を受給できる
• 年金受給者でも最低生活費を下回る場合は生活保護との併用が可能
• 地方都市では都市部より1~2割程度支給額が低くなる傾向がある
• 資産活用と扶養義務者からの援助が生活保護に優先される
• 医療扶助により医療費が完全無料になり高齢者には大きなメリット
• 介護扶助で介護サービスの自己負担分が免除される
• 申請から受給決定まで原則14日以内で調査が行われる
• 受給中は収入申告義務があり虚偽申告は不正受給となる
生活保護は国民の権利として認められた制度です。年金だけでは生活が困難な高齢者の方は、一人で悩まず最寄りの福祉事務所に相談してください。適切な手続きを踏めば、安心して最低限度の生活を送ることができます。