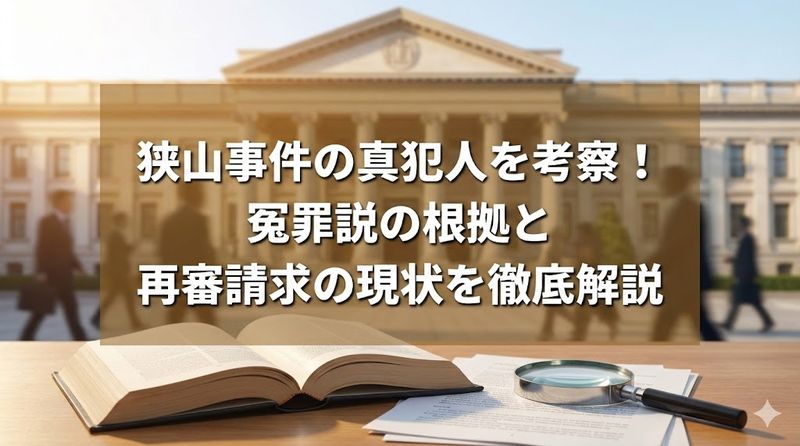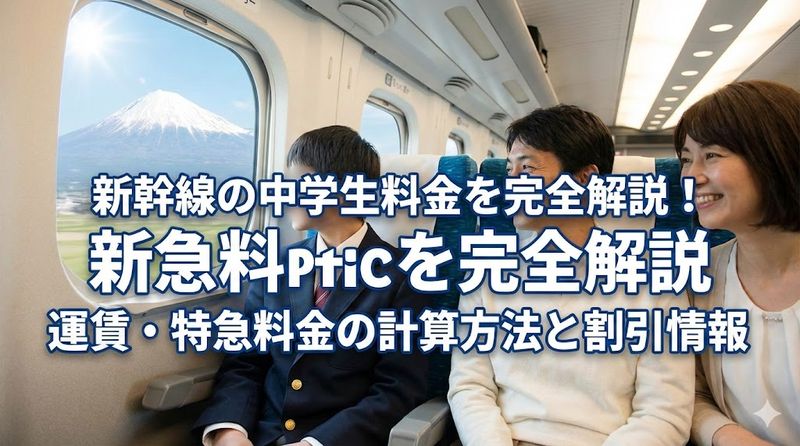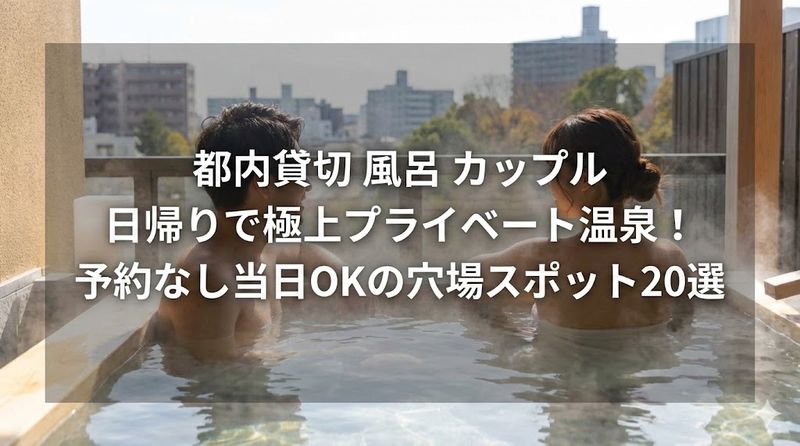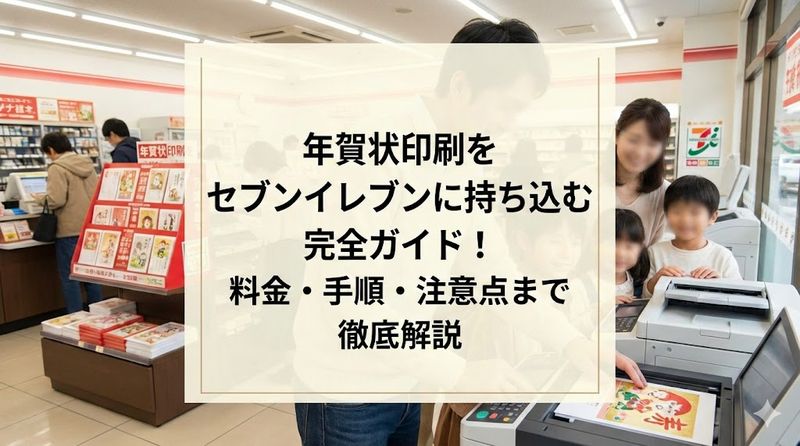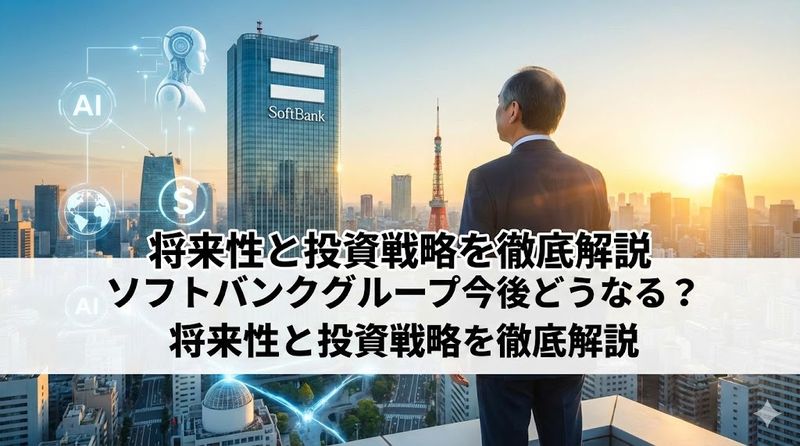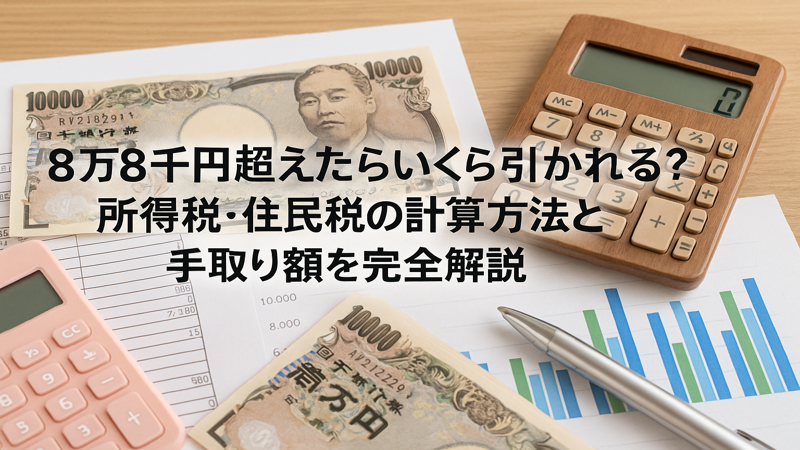
あなたは「月収が8万8千円を超えると税金がどのくらい引かれるのだろう」と心配になったことはありませんか?
結論、8万8千円を超えると所得税や住民税が発生しますが、実際の負担額は収入や扶養状況によって大きく変わります。
この記事を読むことで、具体的な税額計算方法と手取り額がわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。
1.8万8千円を超えた場合の税金の基本知識

所得税の仕組みと8万8千円のボーダーライン
所得税は年収103万円(月額換算で約8万5千円)を超えると発生する国税です。
月収8万8千円を超えた場合、年収換算で105万6千円となり、所得税の課税対象となります。
所得税の計算は「(年収-基礎控除48万円-給与所得控除55万円)×税率5%」で行われます。
月収8万8千円の場合、年間の所得税は約1万3千円程度となり、月割りすると約1,100円が天引きされることになります。
ただし、実際の税額は各種控除の適用状況によって変動するため、個別の計算が必要です。
住民税への影響と計算方法
住民税は所得税とは別に課税される地方税で、前年の収入に基づいて翌年に課税されます。
月収8万8千円を1年間続けた場合、翌年の住民税は年額約5万円(月額約4,200円)が発生します。
住民税の計算式は「(年収-各種控除)×税率10%+均等割5,000円」となっています。
重要なポイントは、住民税は収入が発生した翌年から課税される点です。
そのため、初年度は所得税のみの負担ですが、2年目からは住民税も加わり税負担が増加します。
社会保険料の変動について
月収8万8千円を超えると、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)の負担も増加します。
社会保険料は月収の約14%程度が目安となり、月収8万8千円の場合は約1万2千円が天引きされます。
雇用保険料は月収の0.6%、健康保険料は約5%、厚生年金保険料は約9%がそれぞれ徴収されます。
ただし、勤務時間や雇用形態によって社会保険の加入義務が異なるため、詳細は勤務先に確認が必要です。
パート・アルバイトの場合、週20時間未満の勤務では社会保険に加入しないケースもあります。
扶養控除との関係性
月収8万8千円を超えると、配偶者や親の扶養から外れる可能性があります。
配偶者控除は年収103万円以下、配偶者特別控除は年収201万6千円以下で適用されます。
扶養から外れると、扶養者(配偶者や親)の税負担が年間38万円分増加することになります。
扶養控除の適用を受けたい場合は、年収を103万円以下に調整する必要があります。
ただし、社会保険の扶養は年収130万円以下が基準となるため、税制上の扶養とは異なる点に注意が必要です。
2.具体的な税額計算シミュレーション

月収9万円の場合の手取り額
月収9万円(年収108万円)の場合の手取り額を詳しく計算してみましょう。
所得税は年間約2万5千円(月額約2,100円)、住民税は翌年から年間約5万8千円(月額約4,800円)が発生します。
社会保険料は月額約1万3千円程度が天引きされます。
初年度の手取り額は約7万5千円、2年目以降は約7万円となります。
年収108万円に対する実質的な税負担率は初年度約17%、2年目以降約22%となり、手取り収入が大幅に減少することがわかります。
月収10万円の場合の手取り額
月収10万円(年収120万円)の場合、税負担がさらに増加します。
所得税は年間約3万5千円(月額約2,900円)、住民税は年間約7万円(月額約5,800円)が課税されます。
社会保険料は月額約1万4千円程度となります。
手取り額は初年度約8万3千円、2年目以降約7万7千円となります。
この収入帯では扶養控除の適用も外れるため、世帯全体での税負担増加も考慮する必要があります。
月収12万円の場合の手取り額
月収12万円(年収144万円)になると、税負担がより明確に見えてきます。
所得税は年間約4万8千円(月額約4,000円)、住民税は年間約9万5千円(月額約7,900円)が課税されます。
社会保険料は月額約1万7千円程度が天引きされます。
手取り額は初年度約9万9千円、2年目以降約9万1千円となります。
この収入帯では社会保険の扶養からも外れる可能性が高く、健康保険料の負担も発生します。
年収別の税負担比較表
| 年収 | 所得税(年額) | 住民税(年額) | 社会保険料(年額) | 手取り額(2年目以降) |
|---|---|---|---|---|
| 105.6万円 | 1.3万円 | 5.1万円 | 14.8万円 | 84.4万円 |
| 108万円 | 2.5万円 | 5.8万円 | 15.1万円 | 84.6万円 |
| 120万円 | 3.5万円 | 7.0万円 | 16.8万円 | 92.7万円 |
| 144万円 | 4.8万円 | 9.5万円 | 20.2万円 | 109.5万円 |
この表から、年収が増加するほど税負担率も高くなることがわかります。
ただし、手取り額の絶対値は年収増加に伴って増えるため、収入を抑制するよりも増やした方が経済的には有利となります。
3.8万8千円を超える前に知っておくべき対策
扶養範囲内で働く場合の調整方法
扶養範囲内で働き続けたい場合は、年収を103万円以下に調整する必要があります。
月収換算では約8万5千円以下に抑える必要があり、時給や労働時間の調整が重要になります。
12月の給与調整や有給休暇の取得タイミングを工夫することで、年収をコントロールできます。
ボーナスや賞与がある場合は、それらも年収に含まれるため注意が必要です。
扶養範囲内で働く場合の年間スケジュール管理が重要となり、月ごとの収入をしっかりと把握する必要があります。
確定申告が必要になるケース
月収8万8千円を超えて働く場合、確定申告が必要になるケースがあります。
副業収入が年間20万円を超える場合や、2か所以上から給与を受け取っている場合は確定申告が必要です。
また、年末調整を受けていない場合や、医療費控除などの各種控除を受ける場合も確定申告を行います。
確定申告により、払い過ぎた税金の還付を受けられる場合もあります。
確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までとなっており、期限内の申告が重要です。
副業収入がある場合の注意点
本業で月収8万8千円を超え、さらに副業収入がある場合は税負担がより複雑になります。
副業収入は給与所得ではなく雑所得として計算される場合が多く、税率や控除額が異なります。
副業収入から必要経費を差し引いた所得が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。
住民税については副業収入が少額でも申告が必要な自治体もあるため、確認が必要です。
副業収入がある場合は、収入と経費の記録をしっかりと残しておくことが重要です。
経費計上で税負担を軽減する方法
給与所得者でも、特定の経費については所得控除として計上できる場合があります。
通勤費、研修費、書籍代、制服代などは、条件を満たせば特定支出控除として計上可能です。
副業収入がある場合は、業務に必要な経費を適切に計上することで所得を圧縮できます。
経費として認められるためには、業務との関連性と合理的な金額である必要があります。
領収書や支払い証明書の保管は必須であり、税務調査時の説明責任を果たせるよう準備が必要です。
4.よくある疑問と実際の事例
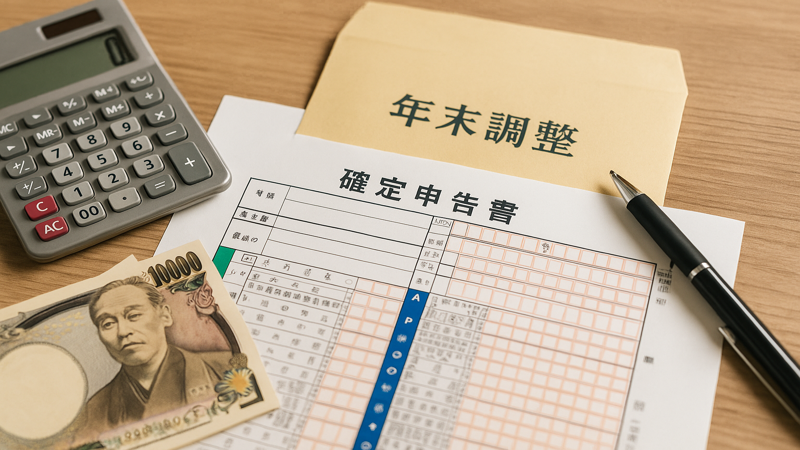
パート・アルバイトでの実例
Aさん(主婦パート)の場合:時給1,200円で月75時間勤務、月収9万円を得ています。
年収108万円となり、所得税約2万5千円、住民税約5万8千円が課税されます。
配偶者控除は適用されませんが、配偶者特別控除により夫の税負担増加は最小限に抑えられています。
社会保険は勤務時間が週20時間を超えるため加入となり、月額約1万3千円の負担があります。
手取り収入は月約7万円となりますが、将来の年金受給額増加も期待できます。
フリーランス・副業での実例
Bさん(会社員+副業)の場合:本業月収15万円、副業(ライター)月収5万円を得ています。
副業収入は年間60万円となり、経費30万円を差し引いた所得30万円が課税対象となります。
副業所得30万円に対して所得税約1万5千円、住民税約3万円が追加で課税されます。
確定申告により副業所得を申告し、源泉徴収された税額との精算を行います。
副業収入が安定している場合は、予定納税の対象となる可能性もあります。
年末調整での手続き方法
年末調整では、生命保険料控除、地震保険料控除、住宅借入金等特別控除などの各種控除を申告できます。
扶養控除等申告書、保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書の提出が必要です。
控除証明書の添付が必要な控除もあるため、事前の準備が重要になります。
年末調整で控除しきれない場合は、確定申告で追加の控除を受けることができます。
正確な年末調整により、適正な税額計算と還付を受けることができます。
税務署への相談が必要なケース
複数の収入源がある場合や、特殊な控除を受ける場合は税務署への相談をおすすめします。
個人事業主として開業する場合は、青色申告承認申請書の提出が有利になります。
海外収入がある場合や、株式投資による収入がある場合も専門的な判断が必要です。
税務署では無料相談を実施しており、電話や窓口での相談が可能です。
複雑な税務処理については、税理士への相談も検討する価値があります。
まとめ
この記事のポイントをまとめると以下の通りです:
・月収8万8千円を超えると所得税約1,100円、住民税約4,200円(翌年から)が発生する
・社会保険料も月額約1万2千円程度の負担が追加される
・扶養控除の適用が外れ、世帯全体の税負担が増加する可能性がある
・手取り額は月収の約78-80%程度になる
・副業収入がある場合は確定申告が必要になるケースが多い
・経費計上により税負担を軽減できる場合がある
・年末調整での適切な控除申告が重要
・複雑なケースでは税務署や税理士への相談が有効
8万8千円を超える収入を得る場合、税負担は発生しますが、手取り収入の絶対値は増加します。適切な知識を身につけて、賢い収入管理を行っていきましょう。
関連サイト
・国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
・日本年金機構公式サイト(https://www.nenkin.go.jp/)