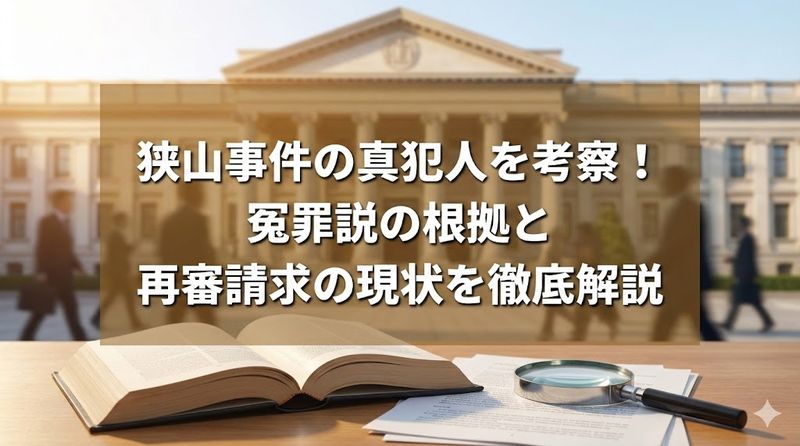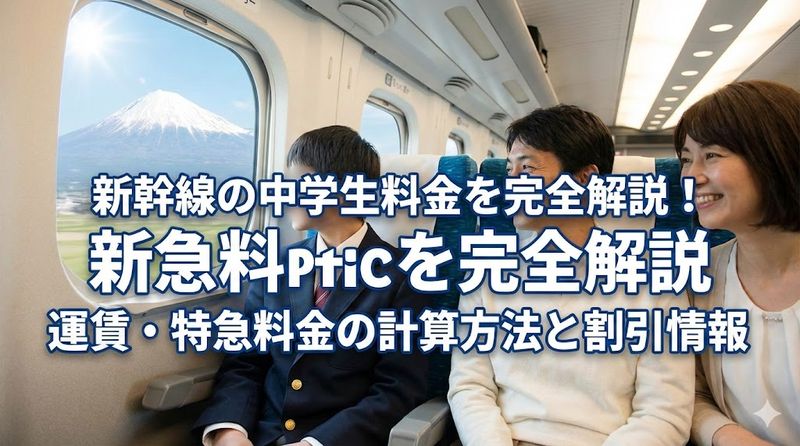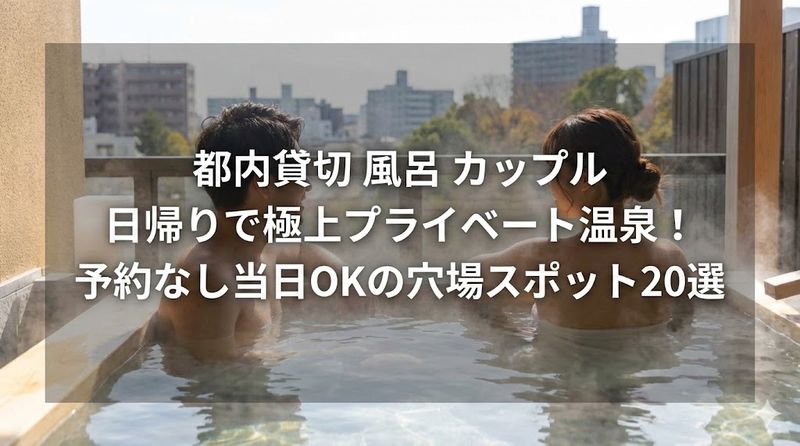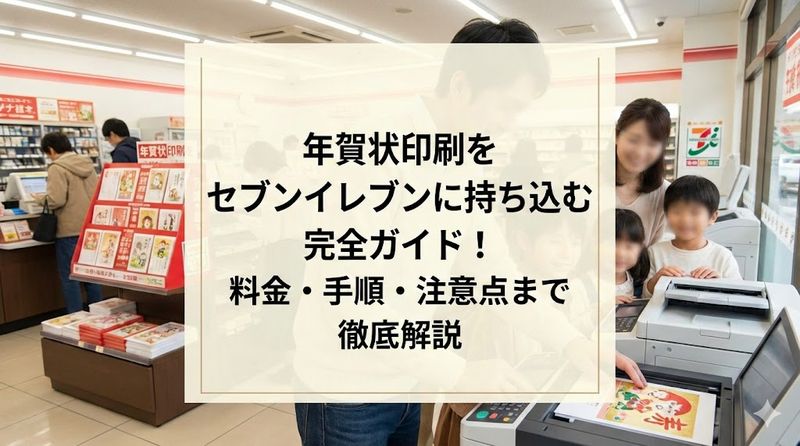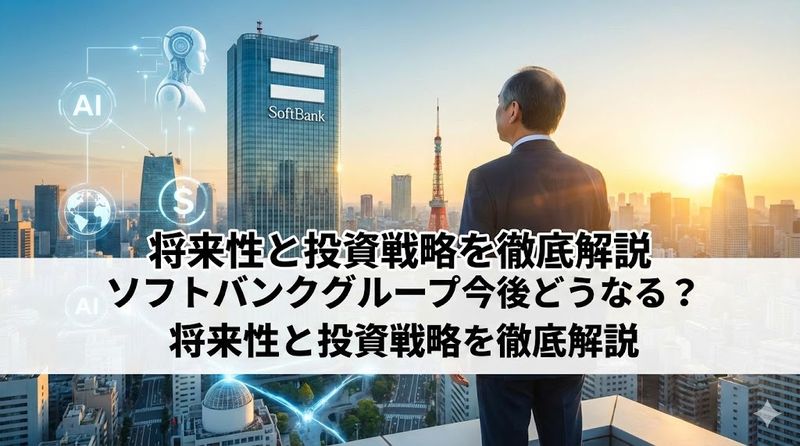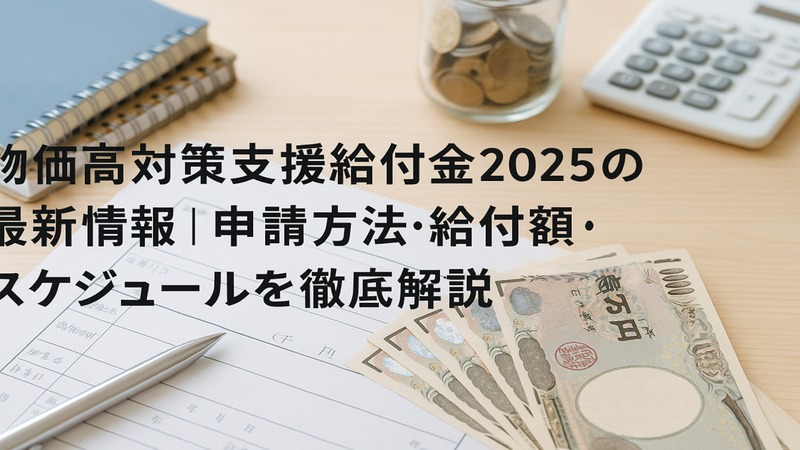
あなたは「物価高で家計が苦しい中、政府からの支援はいつ、いくらもらえるの?」と思ったことはありませんか?結論、2025年は住民税非課税世帯への3万円給付が実施され、さらに一律2万円の追加給付も検討されています。この記事を読むことで物価高対策給付金の申請方法や受給条件、支給時期がわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。
Contents
1. 2025年の物価高支援給付金制度の概要

住民税非課税世帯への3万円給付の詳細
2025年の物価高対策支援給付金は、住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり3万円が支給されます。
この給付金は、令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づいて実施されています。
対象となるのは、令和6年12月13日(基準日)時点で市区町村に住民登録があり、世帯全員が令和6年度の住民税均等割非課税である世帯です。
ただし、住民税が課税されている方に扶養されている被扶養者のみの世帯は対象外となります。
この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税対象外となり、差押えも禁止されています。
子ども1人につき2万円加算の条件
住民税非課税世帯のうち、子育て世帯には追加で手厚い支援が用意されています。
18歳以下の子ども(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯には、子ども1人あたり2万円が加算されます。
例えば、大人2人と子ども2人の4人家族の場合、基本給付3万円+子ども加算4万円(2万円×2人)=合計7万円の支給となります。
児童養護施設や乳児院などに入所している児童も対象に含まれており、幅広い子育て世帯が支援を受けられる仕組みとなっています。
政府の総合経済対策における位置づけ
この給付金は、政府の総合経済対策の重要な柱の一つとして位置づけられています。
事業規模39兆円の経済対策の中核として、物価高への対応が掲げられています。
具体的には以下の3つの柱で構成されています:
- 賃上げ環境の整備などを通じた日本経済・地方経済の成長
- 物価高への対応
- 国民の安心・安全の確保
電気・ガス料金の補助再開と合わせて、家計の負担軽減を図る包括的な支援策となっています。
2. 現在実施中の物価高対策給付金の申請方法

住民税非課税世帯3万円給付の申請手順
多くの自治体では、過去の給付金受給実績がある世帯に対して「プッシュ型支給」を実施しています。
プッシュ型支給の対象となる世帯には、自治体から「ご案内(プッシュ通知)」が送付されます。
この場合、記載されている振込口座に問題がなければ、特別な手続きは不要で自動的に支給されます。
一方、新たに対象となった世帯や転入者などには「申請書」が送付され、必要書類とともに返送する必要があります。
口座変更や給付の辞退を希望する場合は、各自治体のコールセンターまで連絡が必要です。
子ども加算2万円の申請条件と必要書類
子ども加算は、基本給付の3万円と合わせて支給されるのが一般的です。
給付金の案内書類に、子ども加算の対象となる児童名と加算額が記載されています。
新生児が生まれた場合は、基本給付の振込完了後に別途「新生児加算」の案内が送付されます。
必要書類としては、以下のものが求められる場合があります:
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 振込先口座の確認書類(通帳の写しなど)
- 児童の年齢を証明する書類(住民票など)
プッシュ型支給と申請型支給の違い
プッシュ型支給は、自治体が支給対象者を特定し、申請なしで給付金を支給する方式です。
対象となるのは、過去1年程度で低所得世帯向けの臨時特別給付金を受給した世帯などです。
この場合、事前に登録された口座に自動で振り込まれるため、受給者の手間が大幅に軽減されます。
一方、申請型支給は、自治体から送付される申請書に必要事項を記入し、返送する必要があります。
マイナンバーカードを保有している方は、オンライン申請も利用できる自治体が多くなっています。
申請期限と支給時期の詳細
申請期限は自治体によって異なりますが、多くの場合、令和7年5月30日から6月30日頃に設定されています。
支給時期は、申請書類に不備がない場合、申請受理から約4週間程度が目安です。
プッシュ型支給の場合は、令和7年2月から3月にかけて順次支給が開始されています。
オンライン申請の場合は、書面申請よりも早期に支給される場合があります。
申請期限を過ぎると給付を受けられなくなるため、対象世帯は必ず期限内に手続きを完了させることが重要です。
3. 2025年夏の参院選公約で検討される一律2万円給付

全国民一律2万円給付の制度設計
2025年6月、石破首相は参議院選挙の公約として、全国民への一律2万円給付を検討することを表明しました。
この給付案は、所得制限なしで全ての国民を対象とする大規模な現金支給制度となります。
財源については、税収の上振れ分(約1兆5000億円~2兆円)と税外収入(約1兆円)を活用する方針が示されています。
従来の住民税非課税世帯限定の給付とは異なり、中間所得層も含めた全世代型の支援策として設計されています。
赤字国債の発行は行わず、既存の財源内で実施する方針が強調されています。
住民税非課税世帯への追加2万円支給案
一律2万円給付に加えて、住民税非課税世帯の大人にはさらに2万円が追加支給される案が検討されています。
これにより、非課税世帯の大人は合計4万円(基本2万円+追加2万円)の給付を受けることになります。
例えば、夫婦2人が共に住民税非課税の場合、夫4万円+妻4万円=合計8万円の支給となります。
この追加支給は、物価高の影響を最も受けやすい低所得世帯への重点的な支援を目的としています。
非課税世帯の判定は、前年の住民税課税状況に基づいて行われる予定です。
子育て世帯への追加支援の内容
18歳未満の子どもを扶養している世帯には、子ども1人につき2万円の追加支給が検討されています。
この場合、子どもは基本2万円+子ども加算2万円=合計4万円の給付を受けることになります。
例えば、夫婦2人と子ども2人の4人家族の場合:
- 大人2人:2万円×2人=4万円
- 子ども2人:4万円×2人(基本2万円+加算2万円)=8万円
- 世帯合計:12万円
さらに、大人2人が住民税非課税の場合は、追加で4万円が支給され、世帯合計16万円となる可能性があります。
マイナンバーを活用した給付方法
今回の給付では、マイナンバーに紐づく「公金受取口座」への振込が積極的に活用される予定です。
すでに公金受取口座を登録している方は、申請不要で自動的に振込が行われる見込みです。
未登録の方には、自治体から案内書類が送付され、必要書類を提出することで受給できます。
住民税非課税世帯や子育て世帯については、自治体が把握している情報や児童手当の情報と紐づけて支給が行われます。
この方式により、給付事務の簡素化と迅速化が期待されています。
4. 物価高支援給付金2025の受給対象者と条件
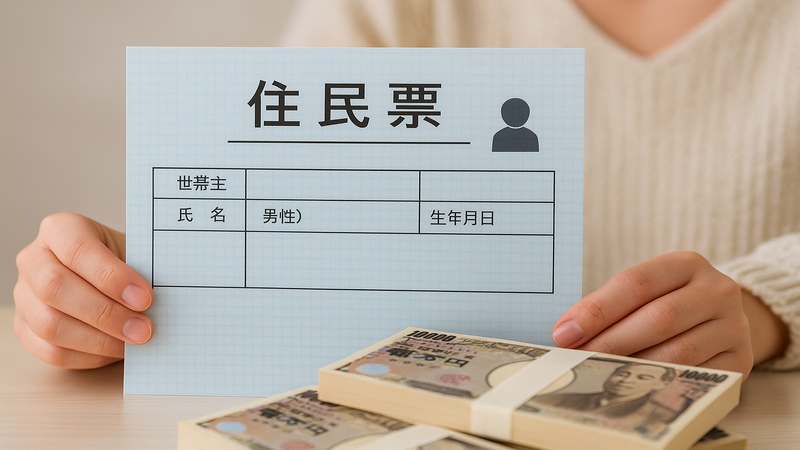
住民税非課税世帯の判定基準
住民税非課税世帯の判定は、世帯全員の令和6年度住民税均等割の課税状況に基づいて行われます。
単身世帯の場合、年収約100万円(所得45万円)以下が非課税の目安となります。
夫婦世帯の場合、年収約156万円(所得101万円)以下が非課税の目安です。
扶養家族がいる場合は、1人増えるごとに35万円が加算されます。
条例により住民税均等割が全額免除されている方も対象に含まれます。
ただし、住民税が課税されている方に扶養されている被扶養者のみの世帯は対象外となります。
18歳以下の子どもの定義と対象年齢
子ども加算の対象となる「18歳以下の子ども」は、平成18年4月2日以降に生まれた方です。
令和7年5月30日(申請期限)までに生まれた新生児も対象に含まれます。
以下の児童も対象となります:
- 児童養護施設に入所している児童
- 乳児院に入所している児童
- 障害児入所施設に入所している児童
- 児童心理治療施設に入所している児童
ただし、他の自治体において既に本給付金の対象となっている児童は除外されます。
扶養関係による除外条件
住民税が課税されている方に税法上の扶養を受けている場合は、給付対象から除外されます。
例えば、以下のようなケースは対象外となります:
- 市外の親(課税者)に扶養されている一人暮らしの大学生
- 単身赴任中の方(課税者)に扶養されている家族
- 地方税法の規定による青色事業専従者および事業専従者
扶養関係については、税務署や市区町村の住民税担当部署で確認することができます。
転入者と国外入国者の取扱い
基準日(令和6年12月13日)に住民登録がある方が対象となります。
転入者の場合、転入前の自治体への税情報照会が必要となるため、支給時期が遅れる可能性があります。
国外から入国した方については、基準日に住民票があり要件を満たす場合は対象となります。
ただし、令和6年1月2日以降に入国した方で、令和5年中に住民税が課税となる所得相当の収入があった場合は対象外となります。
DV等を理由に避難されている方については、特別な配慮措置が設けられています。
まとめ
2025年の物価高対策支援給付金について、以下の重要なポイントをまとめました:
- 住民税非課税世帯への3万円給付が現在実施中で、子ども1人につき2万円が加算される
- 全国民一律2万円給付が2025年夏の参院選公約として検討されている
- 非課税世帯の大人には追加2万円、子どもには追加2万円の支給が検討されている
- マイナンバーの公金受取口座を活用した迅速な給付が予定されている
- 申請期限は自治体により異なるが、多くが令和7年5月30日から6月30日頃
- プッシュ型支給により、対象世帯の多くは申請不要で自動支給される
- 扶養関係や転入時期により対象外となる場合がある
- 給付金は非課税所得で差押禁止の対象となっている
物価高の影響を受けている家計にとって、これらの支援制度は重要な生活の支えとなります。対象となる方は申請期限を逃さず、確実に受給できるよう手続きを進めてください。最新情報は各自治体の公式サイトで随時確認することをお勧めします。
関連サイト
- 内閣府 経済財政政策 – 物価高対策給付金の公式情報
- デジタル庁 マイナンバー総合サイト – 公金受取口座の登録方法