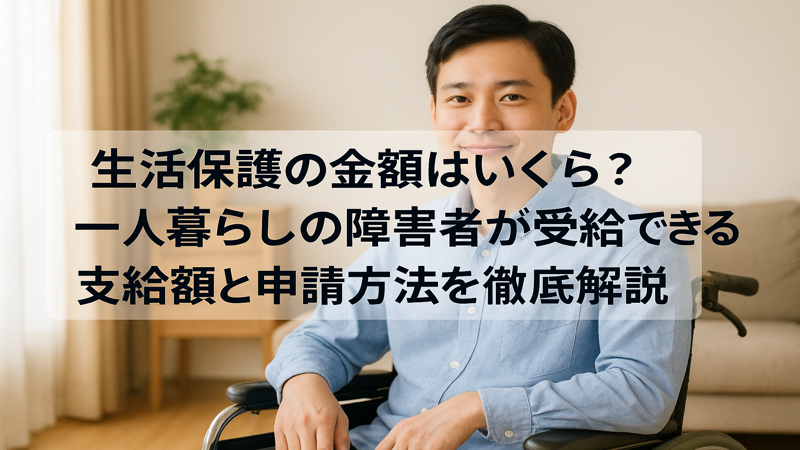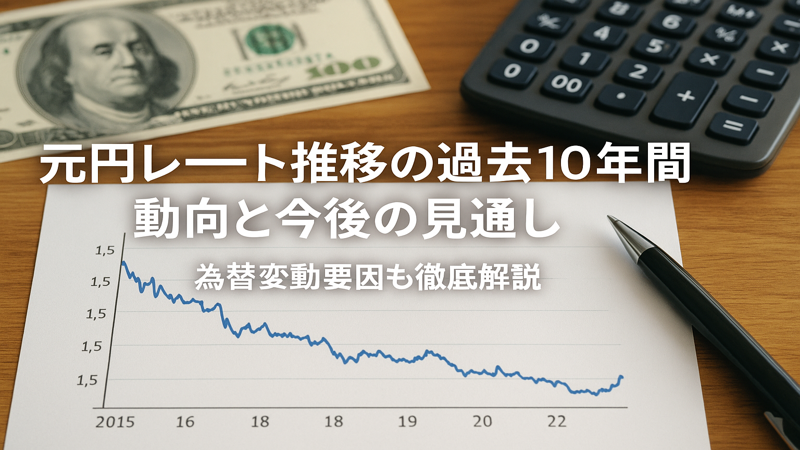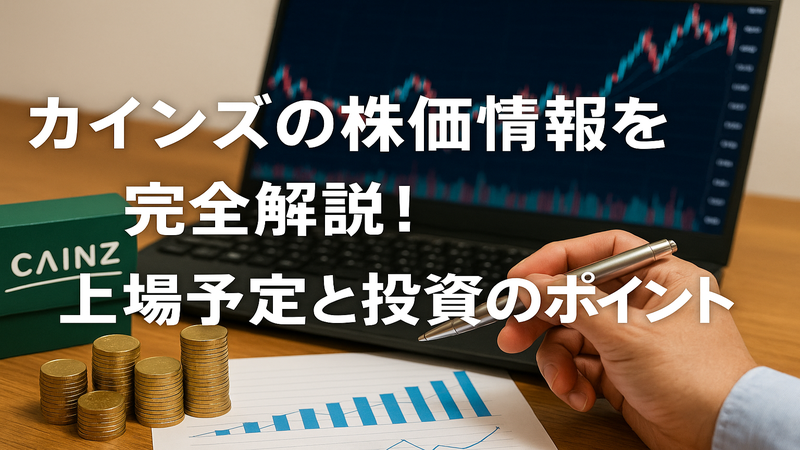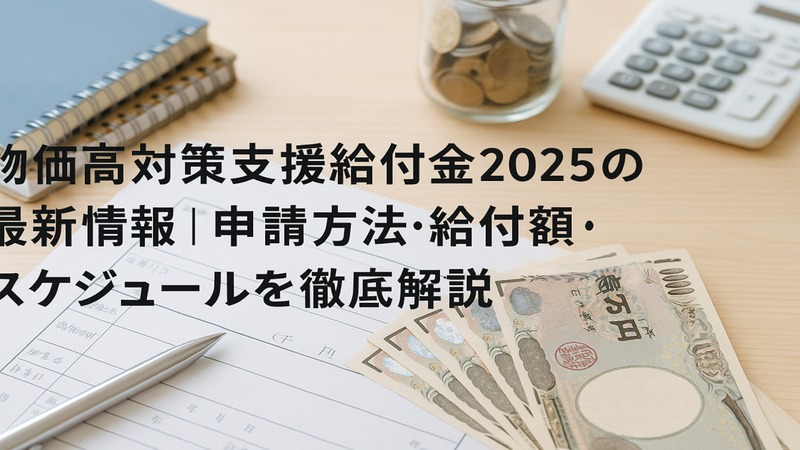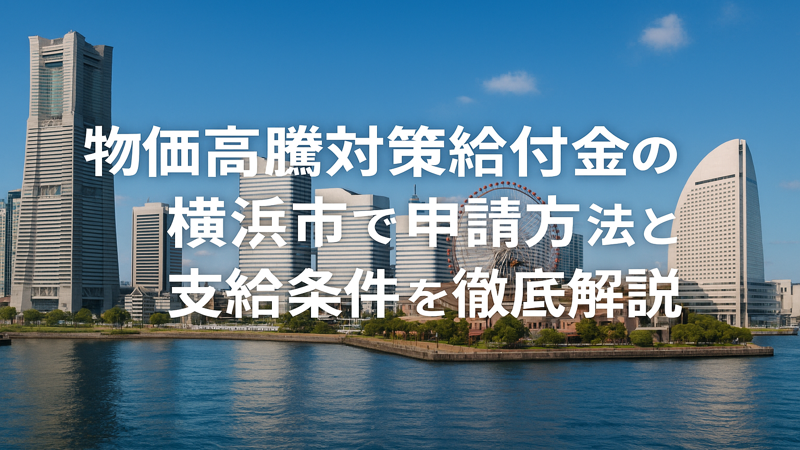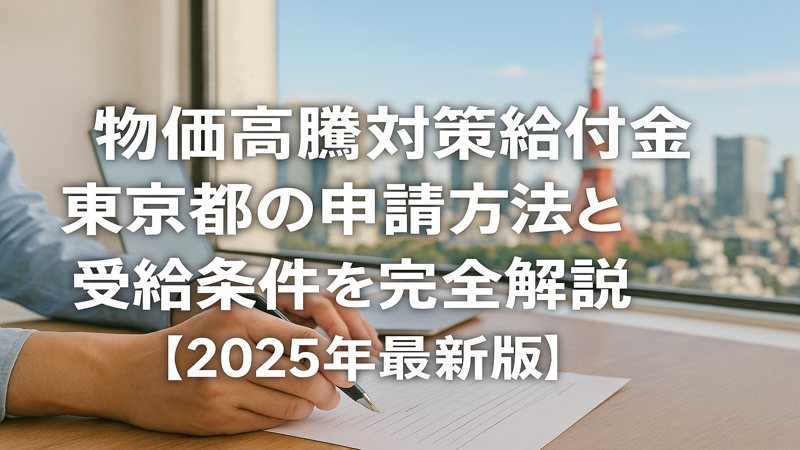
あなたは「物価高騰対策給付金の申請方法がわからない」と思ったことはありませんか?結論、東京都の物価高騰対策給付金は住民税非課税世帯等に1世帯3万円、18歳以下の児童がいる場合は1人あたり2万円を加算して支給されます。この記事を読むことで申請方法や受給条件、支給スケジュールがわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。
Contents
1. 東京都の物価高騰対策給付金の概要と支給金額

物価高騰対策給付金の制度概要
東京都の物価高騰対策給付金は、令和6年12月17日に国会で補正予算が可決された経済対策に基づく給付金です。
物価高騰の影響を特に受けやすい低所得世帯の生活を支援することを目的として、全国の自治体で実施されています。
東京都内の各区市町村では、国の制度に基づいて実施されており、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押えが禁止され、非課税所得として扱われます。
給付金の支給対象となるのは、令和6年12月13日を基準日として、各区市町村に住民登録がある世帯のうち、住民税非課税世帯等の要件を満たす世帯です。
支給金額の詳細(基礎給付とこども加算)
東京都内の物価高騰対策給付金の支給金額は以下の通りです。
基礎給付(世帯単位)
- 1世帯あたり3万円
こども加算(児童単位)
- 18歳以下の児童1人あたり2万円
例えば、夫婦と18歳以下の子ども2人の4人家族で住民税非課税世帯の場合、基礎給付3万円+こども加算4万円(2万円×2人)で、合計7万円が支給されます。
18歳以下の児童とは、平成18年4月2日以降生まれの児童を指し、基準日翌日(令和6年12月14日)以降の出生により初めて住民基本台帳に記録された児童も含まれます。
東京都内各区市町村の独自施策
東京都内の各区市町村では、国の制度に加えて独自の施策を実施している場合があります。
大田区では、令和6年度大田区物価高騰重点支援給付金として、対象世帯に3万円を支給しています。
江東区では、令和6年度住民税非課税世帯への3万円給付に加え、区独自の物価高騰重点支援給付金も実施しています。
新宿区では、物価高騰対策臨時給付金として低所得世帯への支援を行っています。
また、過去には東京都全体の施策として、物価高騰対策臨時くらし応援事業で低所得世帯に1万円分の商品券等を配布した実績もあります。
2. 物価高騰対策給付金の受給条件と対象世帯

住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯の判定基準
物価高騰対策給付金の支給対象となる世帯は、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯です。
住民税非課税世帯の判定基準は以下の通りです。
所得割・均等割ともに非課税となる場合
- 生活保護を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が各自治体の定める基準額以下の方
均等割のみ課税世帯も対象となる場合がありますが、定額減税により住民税均等割のみ課税となる場合は対象外となります。
令和6年度住民税の課税状況は、令和5年1月1日から12月31日までの所得に基づいて判定されます。
支給対象外となる世帯の条件
以下の条件に該当する世帯は、住民税非課税世帯であっても支給対象外となります。
主な対象外の条件
- 住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている者のみで構成されている世帯
- 租税条約による免除の適用を届け出ている者を含む世帯
- 他市区町村で同趣旨の給付金を受給している世帯
扶養親族等のみからなる世帯とは、住民税均等割課税者の扶養親族や配偶者控除・配偶者特別控除の対象となる配偶者のみで構成されている世帯を指します。
この場合、世帯員全員が住民税非課税であっても、扶養者が別にいるため支給対象外となります。
転入・転出がある場合は、基準日(令和6年12月13日)時点での住民登録地の自治体が給付を行います。
18歳以下の児童に対するこども加算の要件
こども加算は、基礎給付の対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に支給されます。
対象となる児童
- 平成18年4月2日以降生まれの児童
- 基準日(令和6年12月13日)時点で世帯主と同一世帯である児童
- 基準日翌日以降の出生により初めて住民基本台帳に記録された児童も含む
住民票上は別世帯でも対象となる場合
- 進学等により学生寮に居住している場合
- 施設入所等により別世帯となっている場合
これらの場合は、別居監護申立書の提出により、生計を一にしている実態があればこども加算の対象となります。
対象外となる児童
- 他市区町村で同内容の給付金を受給している児童
- 令和6年12月13日時点で他の自治体に住民登録がある児童
3. 申請方法と必要書類

プッシュ型給付(手続き不要)と申請型給付の違い
物価高騰対策給付金の支給方法は、プッシュ型給付と申請型給付の2つに分かれます。
プッシュ型給付(手続き不要)
- 区市町村が住民税情報等により支給対象世帯を特定
- 対象世帯に「支給のお知らせ」を郵送
- 世帯主名義の口座(過去の給付金受給実績等)に自動振込
申請型給付(手続き必要)
- 区市町村が課税状況を確認できない世帯
- 年の途中で転入した世帯
- 口座情報の変更が必要な世帯
確認書の提出が必要な場合
- 支給要件の確認が必要な世帯
- 口座情報の登録・変更が必要な世帯
- 受給辞退を希望する世帯
多くの区市町村では、2025年2月中旬から3月にかけて順次支給が開始されています。
確認書・申請書の記入方法と提出方法
確認書や申請書が届いた場合は、以下の手順で手続きを行います。
確認書の記入方法
- 世帯主の氏名・住所等の基本情報を記入
- 振込先口座情報を正確に記入
- 支給要件に関する確認事項にチェック
- 誓約・同意事項を確認して署名
提出方法
- 郵送: 同封の返信用封筒で郵送
- 窓口持参: 区市町村の指定窓口に直接提出
- オンライン申請: 二次元コードまたはURLから電子申請
オンライン申請の場合
- マイナンバーカードと電子証明書(4桁のパスワード)が必要
- 24時間いつでも申請可能
- 書類の郵送が不要で処理が迅速
記入時の注意点
- 振込先口座は世帯主名義の口座のみ
- 口座番号等は正確に記入(間違いがあると振込できません)
- 確認書は黒いボールペンで記入
本人確認書類と口座確認書類の準備
申請時に必要な書類は以下の通りです。
本人確認書類(いずれか1点)
- 運転免許証の写し
- マイナンバーカード(表面)の写し
- パスポートの写し
- 健康保険証の写し
- 年金手帳の写し
口座確認書類(いずれか1点)
- 通帳の口座名義・口座番号が記載されているページの写し
- キャッシュカードの写し
- インターネットバンキングの口座情報画面の写し
追加で必要となる場合がある書類
- 住民税非課税証明書: 令和6年1月1日時点で他市区町村に住所があった場合
- 別居監護申立書: こども加算で別居している児童がいる場合
- 児童扶養手当証書: ひとり親世帯の場合
書類準備の注意点
- 写しは鮮明にコピーし、文字がはっきり読めるようにする
- 複数ページにわたる場合は、すべてのページを提出
- 有効期限がある書類は、期限内のものを提出
DV避難者・別居中の方の特別申請手続き
配偶者からの暴力(DV)等により避難している方や、離婚協議中で別居している方も、一定の条件を満たせば給付金を受給できます。
DV避難者の支給要件
- 基準日時点で避難先の区市町村に居住している
- 各給付金の課税状況の要件を満たしている
- 住民票の異動が困難な状況にある
必要な手続き
- 避難先の区市町村に申し出
- DV避難者用の申請書を提出
- 被害申出受理確認書等の提出
必要書類
- DV避難者用申請書兼請求書
- 本人確認書類の写し
- 口座確認書類の写し
- 被害申出受理確認書(警察・配偶者暴力相談支援センター等発行)
被害申出受理確認書がない場合
- 区市町村の担当窓口で状況を確認
- 事前予約が必要な場合があります
- 後日、申出受理確認書を発行
注意点
- 同一世帯の他の家族が他の自治体で受給している場合は対象外
- 避難の事実と給付要件を満たしていることの両方が必要
- 手続きには時間がかかる場合があるため、早めの相談が重要
4. 2025年最新の支給スケジュールと申請期限

東京都内各区市町村の支給開始時期
東京都内の各区市町村では、2025年1月下旬から3月にかけて順次支給が開始されています。
支給開始済みの主な自治体
- 大田区: 2025年2月上旬から振込開始
- 中央区: 2025年1月から案内開始、コールセンター設置済み
- 栗原市: 2025年1月下旬から支給開始
3月支給開始予定の自治体
- 杉並区: 2025年3月3日から順次支給開始
- 横浜市: 2025年3月7日から順次振込開始
- 静岡市: 2025年3月から支給開始
支給の流れ
- 1月中旬〜2月: 対象世帯への通知書発送
- 2月上旬〜3月: 確認書の発送・返送
- 2月中旬〜3月: 順次振込開始
プッシュ型給付対象世帯は、確認書の提出から約1か月程度で振込が完了します。
申請型給付の場合は、書類の審査に時間がかかるため、プッシュ型給付よりも支給時期が遅くなる場合があります。
申請期限と期限延長の状況
物価高騰対策給付金の申請期限は、多くの自治体で2025年5月30日または2025年6月30日に設定されています。
主な申請期限
- 江東区: 2025年7月31日(期限延長済み)
- 渋谷区: 2025年6月30日
- 武蔵野市: 2025年5月30日
- 調布市: 2025年5月30日
期限延長の状況
- 江東区では、当初の期限から2025年7月31日まで延長
- オンライン申請は当初予定通り2025年5月30日まで
申請期限の注意点
- 期限を過ぎての申請は一切受付不可
- 郵送の場合は必着(当日消印有効ではない)
- 書類不備の修正も期限内に完了させる必要がある
期限間近の対応
- コールセンターでの事前確認を推奨
- 窓口での直接提出を検討
- オンライン申請の場合は時間に余裕を持って実施
振込までの期間と支給完了の確認方法
給付金の振込までの期間は、申請方法や書類の不備の有無により異なります。
振込までの標準的な期間
- プッシュ型給付: 支給のお知らせ発送後約2週間〜1か月
- 確認書提出: 受理から約1か月
- 申請書提出: 受理から約1か月〜1か月半
支給完了の確認方法
-
通帳記帳による確認
- 振込名義: 「○○区ブッカコウトウ」等
- 振込金額: 3万円または5万円等
-
支給完了通知書の受領
- 振込後に郵送される場合があります
-
コールセンターでの確認
- 個人情報保護のため、本人確認が必要
- 世帯主本人からの問い合わせに限定
振込が遅れる場合の原因
- 書類不備: 確認書類の記入漏れ・添付漏れ
- 口座情報の誤り: 口座番号の記入ミス
- 審査の必要: 転入世帯等の課税状況確認
振込エラーの対処法
- 口座が存在しない場合は再度確認書を発送
- 口座名義が異なる場合は修正手続きが必要
- 金融機関の統廃合等による口座変更は速やかに連絡
まとめ
東京都の物価高騰対策給付金について、重要なポイントを整理します。
• 支給金額は住民税非課税世帯等に1世帯3万円、18歳以下の児童1人につき2万円を加算
• 基準日は令和6年12月13日で、この時点での住民登録地の自治体が給付を実施
• プッシュ型給付では手続き不要で自動振込、申請型給付では確認書等の提出が必要
• 申請期限は多くの自治体で2025年5月30日または6月30日、期限厳守が重要
• DV避難者や別居中の方も一定条件を満たせば受給可能
• 給付金は差押え禁止で非課税所得として扱われる
• 東京都内各区市町村で2025年1月下旬から3月にかけて順次支給開始
• 振込までの期間は申請方法により異なるが、概ね1か月程度が目安
• 必要書類は本人確認書類と口座確認書類が基本で、状況により追加書類が必要
• 扶養親族等のみからなる世帯は住民税非課税でも支給対象外となる場合がある
物価高騰の影響を受けている世帯にとって、この給付金は重要な生活支援策です。対象要件を満たしている場合は、申請期限内に確実に手続きを行い、家計の負担軽減にお役立てください。